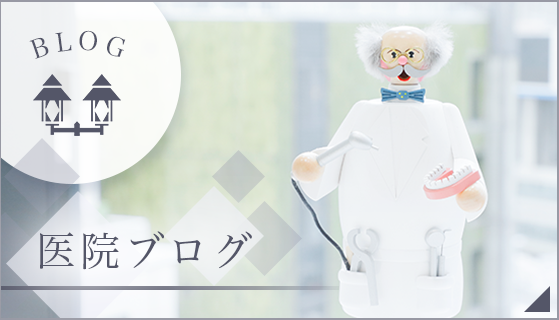矯正治療に伴うリスクとは?
2024年4月16日
歯並びの乱れを整える矯正治療は、かみ合わせを正常化することで歯ブラシによる清掃性を向上させて虫歯を予防する、見た目が美しくなるなど、たくさんのメリットが得られます。
治療期間が長いというデメリットはあるものの、口元に関する悩みや長年のコンプレックスを解消できる素晴らしい歯科治療です。
ただし、矯正も医療である以上、下記のようないくつかのリスクを伴います。
【矯正治療で起こりうる主なリスク】
・強すぎる矯正力で「歯根吸収」が起こることがある
・ワイヤーの材質によっては「金属アレルギー」になることがある
・治療中は「清掃性が低下」し、歯磨きがしづらくなる
・治療中に病気やメンテナンス不足によっては「治療が遅れる可能性」がある
・見た目重視の治療により「咀嚼力が低下してしまう」ことがある
それぞれの内容と原因をご紹介していきます。

予防方法もあるのでご安心ください
矯正治療によるリスクの内容とその原因
歯根吸収
矯正治療に伴うリスクとしては、まず「歯根吸収」が挙げられます。
歯の根っこである歯根が溶ける現象で、原因としては過剰な矯正力が挙げられます。強い力が歯周組織に負担をかけてしまい、歯肉が下がってしまうケースもあるのです。
金属アレルギー
矯正装置に金属材料を使っているケースでは、治療期間中に金属アレルギーを発症するリスクがあります。ブラケットや矯正用ワイヤーの金属は比較的アレルゲンとなりにくい材質ではありますが、それでもリスクはゼロではありません。
清掃性の低下
全ての歯の表側にブラケットを装着するマルチブラケットによる歯列矯正では、装置の構造上、どうしても清掃性が著しく低下します。
歯磨きがしやすくなるように治療をしているのに、治療中はむしろ歯磨きがしにくくなるという矛盾を抱えてしまうのが矯正治療です。
着脱式の装置を使うマウスピース型矯正であれば、歯磨きのときに装置を外すことができるので清掃性に変わりはありません。この点ではワイヤー矯正よりもマウスピース型矯正のほうが大きな優位があると言えます。
予定より治療完了が遅れる可能性
ワイヤー装置を付ける場合、矯正期間中に虫歯や歯周病になると、まずはそれらの治療を優先する必要があります。
一度装置を外して、虫歯治療や歯周病治療に専念するため、矯正の治療計画に大幅な乱れが生じます。その他、メンテナンスを怠ったり、装置の装着時間を守らなかったりすると、予定通りに歯が動かなくなることもあるので注意しましょう。

定期的に通院してきちんと歯が磨けているかチェックするのも重要です
治療方法次第で咀嚼力が低下
しかし、一番重要視しなければいけないのは、矯正の結果咀嚼力が低下するリスクです。これは見た目を重視し、噛み合わせより歯並びばかりに焦点を当てすぎた治療をした場合に起きうることです。
矯正治療は審美的な要素が重視される傾向にありますが、その結果歯の健康を害してしまっては本末転倒です。
歯並びを整えてしっかり食物を咀嚼したり、食物が歯に挟まりにくくなったりすることで、虫歯や歯周病のリスクを低減させるという最大の目的を決して忘れてはいけません。
矯正治療のリスクは治療方法や予防で抑えることが可能
矯正にはご紹介したようなリスクが伴いますが、いずれも治療方法の選択や適切な予防でリスク発生を抑えられます。
矯正治療の持つリスクを避けつつ、審美的にも口腔内の健康的に満足することができるように治療をするのが、矯正医の治療技術と言えます。

矯正治療に対する不安や疑問は何でも当院にご相談ください
銀座のマウスピース矯正
歯科スケーリングの不安を解消しよう!
2023年11月14日

歯科定期検診やメンテナンス、歯周病治療において、スケーリングは欠かせない処置です。この記事では、スケーリングについての不安を取り除き、正確な情報を提供します。
歯周病にかかっている人のスケーリングでは、歯茎からの出血や痛みがあることがあります。これは歯周病によって歯茎が腫れ、刺激に敏感になるためです。しかし、歯茎を傷つける心配はありません。歯の表面に細かい傷や亀裂がある場合、スケーリングが少ししみることがありますが、これは一時的なものです。知覚過敏を感じたら、歯科医師や歯科衛生士に伝えてください。対処方法を提供します。

Before: 歯石が多量に付着している

歯石が除去され歯の表面もきれいに汚れが取れている
スケーリング後、歯茎が引いたように見えたり、歯と歯の間が広がったように感じることがあります。これは歯石の取り除きにより、歯茎の炎症が改善されるためです。歯茎が元の状態に戻り、歯茎の腫れが減少することがあります。これは正常な反応であり、心配する必要はありません。
スケーリングは簡単な処置ではないかもしれませんが、歯の健康にとって重要なものです。不安を感じる場合、歯科衛生士や歯科医師に相談しましょう。処置の詳細を説明してもらうことで不安が解消します。
歯科スケーリングは歯石を取り除き、歯周病を管理するための重要なステップです。正確な情報とプロのアドバイスを受けて、不安を取り除きましょう。歯の健康を守るために、定期的な検診とメンテナンスが必要です。

アイコンによるホワイトスポットの修復
2023年8月19日

Before

After
歯の表面に見える白い斑点は「ホワイトスポット」と呼ばれ、多くは初期の虫歯を示しており、歯のエナメル質が酸性化しカルシウム成分が減ることで、歯の表面に白濁したホワイトスポットを形成することで生じます。
ホワイトスポットは、ホワイトニングではなくならず、かえって目立つことさえあります。この問題を解決するためには、歯を削ったり、カルシウム補給用の歯磨き粉を使ったるするような方法か、ラミネートべニアというセラミックの薄片で隠す以外ありませんでした。
しかし、アイコンという方法では、特別な薬剤を使って脱灰したエナメル質を補強します。これにより、歯を削ることなくホワイトスポットを改善し、再発を防ぐことができます。この症例では白濁したホワイトスポットが透明感を取り戻し、周りの歯の表面と区別がつかなくなっています。
費用:1歯 33,000円(同時2歯目からは1歯16,500円)
リスク:・ 露出した象牙質又はセメント質がある場合、痛みを生じる可能性があります。
・歯の先端部に帆愛とスポットがあると形状の変化が起きることがあります。
こちらもご参照:
中野の歯医者_マナミ歯科クリニック

矯正はどうやって歯を動かすのか【ワイヤ矯正・マウスピース矯正の方法】
2023年8月10日
矯正治療は歯並びの悪さを治すための治療
歯並びが悪いと見た目が良くないだけでなく、歯にプラークが付着しやすく、虫歯や歯周病になりやすくなります。
歯科治療費が日本と比べ高い欧米で矯正治療が日本より普及しているのは、美的な理由だけではありません。
将来歯科治療が必要になるリスクをできるだけ避けようとしているという大きな理由があるのです。
とはいえ、歯の矯正の需要さがわかっても、「なんだか怖い」と漠然とした不安で矯正治療をためらっている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、歯の矯正は具体的にどういった方法で行うのか、歯を移動させる原理などを簡単にご紹介していきます。
歯の移動のさせ方はワイヤ矯正・マウスピース矯正とも同じ
矯正治療には、歯にワイヤを(ブラケット)を装着する「ワイヤ(ブラケット)矯正」と、マウスピースを装着する「マウスピース矯正」の2種類の方法があります。
ワイヤは毎月の調整で少しずつワイヤの形を変えて歯を移動させるのに対し、マウスピース矯正はマウスピースを2週間程度ごとに交換して、目標とする歯並びに近づけていきます。
ワイヤ矯正もマウスピース矯正も歯に圧迫を加えることで少しずつ歯を移動させるのです。
ではどうしてこれらの方法で歯が移動するのでしょうか。
歯は歯茎の中で歯根膜と呼ばれる膜に覆われたうえで、骨(歯槽骨)に固定されています。
その歯が一定方向の力で押されると、押されている方の歯槽骨が吸収され、反対側の歯槽骨では逆に骨の造成が行われます。
つまり、矯正治療は歯の圧迫による骨の吸収と造成により、歯が移動することを利用しているのです。
矯正に年齢制限はありません
骨の吸収と造成は、新陳代謝が行われている限り年齢に関係なく起こります。
矯正治療には年齢制限があるとお考えの方もいますが、新陳代謝は年を取っても活発さが衰えることはあっても、なくなることはありません。
実際、50~60歳で矯正治療を始める例も少なくないのです。
年齢が理由で「今さら矯正を始めても…」と迷っているという方は、ご安心ください。
矯正治療後は逆戻りさせないようにリテイナーの装着が必須
ところが、せっかく矯正治療をしても、後戻りが起きることがあります。
その理由は歯と歯槽骨の間にある歯根膜が骨ではなく腱のような組織だからです。
歯が骨の吸収・造成で移動すると、移動する方向の横歯根膜は移動する方向に引っ張られる形になります。
そのため、移動した歯には戻ろうとする力が加わるのです。
こういった歯の逆戻りの移動を防ぐためには、リテイナーと呼ばれる下の画像のような装置を矯正終了後のしばらくの期間で装着する必要があります。

これがリテイナーです

リテイナーにはマウスピースタイプのものもあります
ワイヤ矯正、マウスピース矯正どちらも歯を動かす基本は同じで、後戻り対策にリテイナー装着を行う必要があることにも変わりません。
【ワイヤ矯正、マウスピース矯正の違いについては他の記事を参考にしてみてください】
長い年月のかかる矯正治療も短期間で可能な時代
マウスピース矯正はなぜブームになったのか
ワイヤー矯正とマウスピース矯正とは?これから矯正をする方へ
矯正治療は、抜歯?非抜歯?
八重歯を放置しているとデメリットが多い?しっかり治すのがおすすめ
「良い抜歯」と「悪い抜歯」とは?
どうしても抜歯しないようにするにはどうすればいい?
姿勢と歯の関係は?
銀座の矯正歯科は銀座並木通り歯科
ボツリヌス菌製剤は、歯ぎしりに効果があるのか?
2023年7月29日

歯ぎしりは無意識に強い力を歯や歯茎にかけてしまいます
歯ぎしりには、ボツリヌス菌製剤、正確にはボツリヌストキシン製剤が有効です。
一般にはアロガン社の商品名であるボトックスの方が知られているでしょう。
(セロハンテープでもっとも有名な商品名「セロテープ」のようなものですね。)
この記事では、なぜボツリヌス菌製剤が歯ぎしりに効果があるのかを、ボツリヌス菌との歴史と併せて解説していきます。
歯ぎしりに悩んでいる方はぜひご一読ください。
ボツリヌス菌製剤の歴史
「そもそもボツリヌス菌って何?」という疑問をお持ちの方も多いと思います。
まずはボツリヌス菌の特性や、その特性を逆手にとった例を軽くご紹介していきましょう。
ボツリヌス菌は本来強い毒性を持つ菌
ボツリヌス菌は極めて強い毒性を持っていて、食中毒の原因菌として知られてきました。
ボツリヌストキシンはこのボツリヌス菌が生成する毒性成分の名前です。
また、この強い毒性は生物化学兵器の材料とされることもあります。
その危険なボツリヌストキシンが医療用として使われるようになったのは、毒性のメカニズムそのものが利用できるということがわかってきたからです。
ボツリヌストキシンは神経の伝達物質を阻害します。
つまり、ボツリヌストキシンは神経が働くなることで四肢や呼吸が麻痺することで毒性を発揮するのです。
あえて神経の働きを阻害させることで医療や美容にも有効
このような本来は恐ろしい特性を持つボツリヌストキシンですが、あえて神経の働きを妨害することで、さまざまな医療用途もあります。
当初は、斜視や顔面痙攣の防止、あるいは多汗症の抑制などに使用されました。
そして、次第に神経の働きを妨害すること、つまり筋肉を弛緩させるという作用が、美容分野でも注目されるようになりました。

ボツリヌストキシン製剤は皺とり効果で美容に広く利用されています
たとえば、皺とりです。
皮膚を切り取って引っ張るような外科的方法ではなく、ボツリヌストキシンの筋肉弛緩の作用を利用する内科的な療法効果があることがわかり、注目されてきました。
現在では、ボツリヌストキシン菌製剤の美容目的での使用は、年間数百万例に達していると言われています。
そしてそれだけ多数のボツリヌストキシン菌製剤が使用されているにもかかわらず、大きな事故の報告はありません。
ボツリヌストキシン菌製剤の安全性は、多くの実績に裏付けられていると言ってよいでしょう。
ボツリヌストキシン菌製剤が歯ぎしり・喰いしばりに有効な理由
そのボツリヌストキシン菌製剤を歯ぎしり、喰いしばりのような歯科分野で活用することは比較的最近始まりました。
歯ぎしりや喰いしばりの直接の原因は筋肉の過度の緊張なのですが、ボツリヌストキシン菌製剤の筋肉弛緩作用が有効と考えられるようになったのです。
ボツリヌストキシン製剤は歯ぎしりそのものを止めてくれます。
ボツリヌストキシン製剤の使用開始以前は、歯ぎしり、喰いしばりにほとんど唯一有効な対症療法は、ナイトガード(マウスピース)でした。
しかし、ナイトガードは装着が面倒ですし、睡眠中に唾液が溜まりやすいといった不快な現象も発生します。
さらにTCH(Tooth Contact Habit:上下の歯をくっつけてしまう癖)のように、昼間に歯をこすり合わせるような症状には対応できません。

マウスピースは歯ぎしりの対症療法としては有効なものの…
ボツリヌストキシン製剤の歯科分野での応用の歴史はまだ短いです。
しかし、歯ぎしりや喰いしばりが歯や歯茎に与えるダメージが大きいにもかかわらず、本質的な治療法が長年確立されていなかったことを考えると、今後は広く利用されるようになると予想できます。

銀座並木通り歯科HP
入れ歯だってちゃんと噛める!【認知症につながると不安な方へ】
2023年5月21日
歯を失うとインプラントやブリッジといった欠損した歯を補う治療をします。
入れ歯もその中の一つです。
失った歯の数が多くなるとブリッジは難しくなりますし、天然歯に近い咀嚼力を持つという点ではもっとも優れているインプラントでは、インプラントのチタンネジを埋入する土台となる骨が歯周病などによって歯槽骨が失われ不足している場合は、適用が難しくなります。(ただし、骨の増成により、かなりのケースではインプラントが可能です)。
入れ歯はこういったケースの際に有効な治療にはなりますが、入れ歯に対する抵抗感を持つ人は少なくありません。
この記事で、入れ歯で欠損した歯を補うことへの不安点を解消していきましょう。

入れ歯は皆同じ?いいえ違います
入れ歯への不安や抵抗感にはどんなものがある?
それでは入れ歯で考えられるリスクにはどんなものがあるのでしょうか。
もっとも大きい懸念点は咀嚼力の低下
「装着すると違和感がある」「痛い」「食べ物の味が違って感じられる」「入れ歯が動くのが不快」など、入れ歯への不満と悩みは多く寄せられます。
また、8020運動で「80歳に20本以上の歯を残すことが認知症を防ぐことにもなる」という認識が広まってきたため、入れ歯にすることで認知症につながるのではと考える方さえ多くいるのが現状です。
歯を残すことが認知症の防止につながるというのは、咀嚼力が維持されるかどうかにかかってきます。
確かに、入れ歯にすることで咀嚼力が落ちてしまった場合は、食べるものが制限される、あるいは食べることそのものの楽しみが減ることで、活動的な生活がしにくくなり認知症の進行を早めることになりかねません。

食事は人生の楽しみ。決して軽視してはいけません
入れ歯の固定方法次第では咀嚼力低下につながる恐れがあります
入れ歯で違和感を覚えたり、咀嚼力に不満が出たりする理由はいろいろあります。
もっとも大きい不満と言えば、入れ歯がしっかりと固定されていないばかりに、硬いものを天然歯のように噛み切ることができないという点です。
これは、入れ歯が金具(クラスプ)で歯に留められていて、いわば歯茎の上に乗ったような装着をしてしまっているからです。

入れ歯はクラスプで歯に留められています
また、入れ歯固定剤でなるべく動かないようにすることで、かえって固定剤の厚みで入れ歯の位置が一定しなくなったり、不潔になってしまったりというリスクにもつながります。
これに対し、インプラントはチタンネジを骨に固着した上に人工歯を装着するので、場合によっては天然歯以上に強く咀嚼することができます。
実際、インプラントはあまりに強く固定されるため、インプラントの対合歯(反対側の歯)の天然歯が痛んでしまわないように、噛み合わせを慎重に考慮して装着しなければいけないほどです。

インプラントでは人工歯はチタンネジの上に固定されています
入れ歯の固定の仕方を変えれば咀嚼力もしっかり回復します
しかし、保険適用に限らなければ、入れ歯にもインプラントに迫るようなしっかりとした咀嚼力を回復できる方法があります。
一つは「マグネット・デンチャー」と言われる方法で、留め金(クラスプ)の代わりに歯(支台歯)につけた磁石と磁石同士で入れ歯を固定させます。
マグネットデンチャーなら、固定する力が非常に強く、噛み合わせの位置も安定させることが可能です。
また、支台歯がない場合はインプラントを埋入し、それに磁石を装着するという方法もあります。
インプラントと入れ歯の両方を使うことで、インプラントに迫る咀嚼力を得ることができるのです。
もう一つは「コーヌスデンチャー」と呼ばれるタイプです。
コーヌスデンチャーは歯に内冠を付けて、茶筒の蓋をかぶせるように入れ歯を装着します。
茶筒の蓋を引っ張り上げようとすると外気の力でなかなか抜けないように、コーヌスデンチャーも強く固定され簡単に外れるということはありません。

コーヌスデンチャーの内冠
このように保険適用でない方法であれば、入れ歯でも硬いものを咀嚼できる可能性が高いです。
保険適用外の入れ歯の固定方法でも費用はそれほどかかりません
保険適用外となると費用が気になる方も多いかと思いますが、多くの場合で入れ歯は多数のインプラント埋入を行うよりも安く済みます。
また、外科処置をしなくて済みますし、顎の骨の厚みといった制限が少ないため、内科的疾患を考慮する必要もあまりありません。
より幅広い方が咀嚼力を回復できる可能性が高い方法と言えるでしょう。

銀座の入れ歯なら銀座並木通り歯科
口臭が気になる方は必読!口臭の原因は実はかなり幅広いです
2023年4月11日

口臭があるのに気づかない、ないのに気になる、どちらも問題です
口臭を気にする方はたくさんいます。
逆に周りから「口が臭い」と思われているのに、本人はほとんど自覚がない場合もあります。
口臭についてはすでに本ブログ記事「お口の臭いが気になりますか?」に主として口腔内に起因する口臭の対処法を書いておりますので、そちらも併せてご覧ください。
また、マナミ歯科クリニックでは、口臭専門外来・歯科ドックといった口臭に悩む方への治療を提供しています。
上記記事で述べたように、口臭の原因の大部分は口腔内、特に舌苔、歯周病、虫歯が大半を占めます。
つまり、口腔ケアに気をつけることで大部分の口臭は解消できるのです。
今回は少し範囲を広げて、口腔内だけでない口臭の原因に目を向けてみましょう。
口臭の原因は「病的口臭」から食事・ストレス・加齢まで多種多様
口臭の原因は大きく分けて、「病的口臭」つまり、何らかの疾患がある場合と、口臭、病気はなくても食事やストレス、起床時、加齢などの「口の中の状態が変化することによるもの」の二つに分けられます。
病的口臭は副鼻腔炎やガンが起因する場合もあります
病的口臭の原因の大部分は口腔内にあるのですが、副鼻腔炎のような耳鼻科にかかわるもの、さらには糖尿病、感疾患などの内臓疾患に関係するものもあります。
ちなみに、ガン患者には卵の腐ったような臭いやきつい花の臭いのような独特な臭いがあることがあり、ガンの発見に犬を使う研究があるほどです。
唾液分泌の減少も口臭の原因に

食事や歯磨きで口臭が消えるなら唾液分泌が口臭の原因の可能性が高いです
生理的口臭には、ストレスによる口臭もあります。
「恐怖で口がカラカラになる」といった言い方をしますが、ストレスで唾液の分泌が阻害されると、口臭の原因となる嫌気性の細菌を唾液が洗い流せなくなり、口臭が強くなることが原因です。
この唾液の分泌の減少は、生理的口臭の原因の主因とも呼べるものです。
唾液分泌の減少はストレスだけでなく月経や妊娠あるいは思春期のホルモンバランスの急激な変化、加齢(特に更年期)でも起きますし、起床時に口が渇いて口臭がするのもその一種と言えます。
ただし、唾液分泌の減少による口臭は、単純に水分を摂る、あるいは歯磨きをするといったことで大半が解決します。
食事を摂ると口臭がなくなる場合は、唾液の分泌減少が口臭の原因と考えて良いでしょう。
自分に口臭があると思い込んでしまう「自臭症」の可能性も

口臭がないのに口臭を感じる場合は知人恐怖症の一種の可能性もあります
しかし何の原因もないのに口臭を感じる、そもそも口臭そのものがなくても口臭があるように感じるという自臭症あるいは自己臭恐怖症と呼ばれる症状もあります。
これは対人恐怖症の一種で、重症の場合は強迫神経症やうつ病に至ることもあるのです。
そこまで、ひどくなくても「自分に口臭があるのでは」と思って人と接することをためらう人は少なくなく、特に女性には多い傾向にあります。
もちろん、「自分に口臭があるのでは」と悩んで社会的な接触を避けるようになるのは良いことではありません。
悩む前に口臭専門外来で一度検査してみませんか。
生活や人間関係に支障をきたしてしまう前に、的確な診断や治療を受けてみることをおすすめします。
銀座の歯医者なら銀座並木通り歯科
長い年月のかかる矯正治療も短期間で可能な時代
2023年3月14日

ワイヤー矯正治療は毎月ワイヤーの形を変えて歯を動かします
歯並びの乱れを整える歯列矯正は、数年単位の治療期間を要するケースがほとんどです。
これは一般的な虫歯や歯周病の治療とは比較にならないほど長いものです。
それだけに、矯正治療を受けようかどうか迷われている方もいらっしゃることかと思います。
しかし、現在は短時間での矯正治療を行えるケースも増えてきました。
矯正治療の長さがネックで治療を受けるか迷っている方は、ぜひ当記事を最後までお読みください。
歯列矯正はなぜ長い時間が必要なのか
まず知っておいていただきたいのが「歯列矯正には長い時間が必要な理由」です。
そもそも歯は顎の骨にしっかり固定されている
私たちの歯は、歯茎や歯根膜、歯槽骨などによって支えられています。
これらを総称して「歯周組織」といいます。
食事の際に硬いものをしっかり噛めるのも、それぞれの食材が持つ食感を楽しむことができるのも、この歯周組織が歯をしっかりと支えてくれているおかげです。
また、永久歯は一生涯使い続ける歯でもあることから、そう簡単に歯がグラついたり、移動したりしても困ります。
そのため、歯は顎の骨にしっかりと固定されているのです。
矯正治療は歯を損傷させずにゆっくりと移動させる治療
そんな歯を矯正装置によって強引に移動させるのが「歯列矯正」です。
とは言え、単に強い力を加えても、歯は思うように動いてくれません。
骨というのは、激しい変化に対応できる組織ではないため、力を加えてもその部分の歯や骨が折れるといった外傷を負ってしまうだけです。
そこで注目されるのが、歯列矯正における力の加え方です。
エッジワイズ法に代表される「ワイヤー矯正」では、弱い力を加えながら、少しずつ歯を動かしていきます。
その結果、歯の移動方向では骨が吸収し、後方では骨の再生が起こるのです。
これを「骨のリモデリング」といいます。
歯槽骨という硬い組織に埋まっている歯を適切に移動させるには、この現象を繰り返していく他ないのです。
この治療を無理やり短縮させても上手くはいきません。
強い矯正力を加えて、3年の治療期間を1年に短縮しようとすると、骨が吸収されていくばかりで再生が追いつかず、歯列矯正自体が失敗に終わります。
そして、こうした強引な処置は、顎の骨が壊死させたり、歯根が吸収されたりといったリスクも出てきてしまいます。
ご説明した通り、歯列矯正というのは、骨のリモデリングという生理現象に基づいて行われるものであるため、長い治療期間が必要です。
生まれ持った歯並びを人為的に変化させるというのは、それくらい大変なことなのです。
大幅に歯の矯正治療期間を短縮してくれる画期的な「IGOシステム」

IGOが適用可能なら3~6カ月で矯正治療ができます
この原理はワイヤーを使用しない「マウスピース矯正」でも同様です。
しかし、インビザラインという製品名で知られるマウスピース矯正における世界トップメーカーのアランテクノロジー社は、歯の大きな移動を必要とせず、3~6か月で矯正を終了する「IGOシステム」を開発しました。
IGOは膨大な矯正用マウスピースの作成に使ったビッグデータをコンピューターで解析します。
そして、この解析結果をもとに、矯正の検査時に必要なマウスピースを設計・製造するという画期的な方法を用いることで、短期間での治療終了を実現しているのです。
ただし、残念ながらすべてのケースでIGOが適用できるわけではありません。
矯正で歯の移動スペース確保のために抜歯を行う「便宜抜歯矯正」をする場合だと、マウスピース矯正でも年単位の時間がかかってしまいます。
また、IGOが適用可能かどうかは「Itero」と呼ばれるコンピューターの診断装置で判断する必要があります。
短時間で矯正治療を行える可能性もありますので、ぜひ歯科医院での検査とカウンセリングでお確かめください。
銀座の矯正歯科は銀座並木通り歯科
虫歯菌と歯周病菌について~虫歯と歯周病になる仕組みを解説~
2023年2月4日

虫歯と歯周病は代表的な口の中の疾患です。
虫歯は強い痛みがありますし、過去に治療で歯医者に行ってガリガリ削られたりしたことで「歯医者は痛い」「歯医者は怖い」といった印象の元になっている方が多いかもしれません。
一方で、歯周病は痛みがないまま症状が進行してしまうため、「サイレントキラー」という恐ろしい名前が付いています。
このように、対照的な虫歯と歯周病ですが、どちらも細菌が引き起こす感染症です。
とは言え、人は口の中に何百種類もの細菌を持っています。
そのため、感染症とは言っても、元々自分の口の中に持っていた細菌が引き起こすことがほとんどと言ってよいでしょう。
今回はこの虫歯菌と歯周病菌の特徴や虫歯・歯周病になってしまう原因を解説していきます。
虫歯はミュータンス菌と糖分が原因で発生
先ほど、虫歯や歯周病などの感染症は「元々自分の口の中に持っていた細菌が引き起こすことがほとんど」と言いましたが、虫歯を引き起こす菌の中で代表的なミュータンス菌は、生まれたばかりの乳児にはありません。
ミュータンス菌は口移しや食器の共用によって主に親から子に感染します。
3歳までミュータンス菌が感染しないように注意をすると、その後口腔内の虫歯菌が増えることはなくなり、かなり虫歯になりにくくなります。
とは言え、ミュータンス菌の感染を幼児の時に遮断するのは簡単ではありません。
残念ながらほとんどの人は虫歯菌に感染してしまいます。
また、虫歯は砂糖などの糖分を虫歯菌が分解して酸性の物質を作ることが原因です。
歯の表面はエナメル質という非常に硬い物質で覆われていますが、エナメル質の主成分は石灰で、酸には弱い物質でもあります。
そのため酸性の物質がエナメル質を溶かしてしまい、虫歯菌を歯の中に侵入させるのです。

歯は唾液中のカルシウム分、リン酸イオンにより再石灰化されます
歯周病は口腔内の細菌が変化したプラークが原因で発生
虫歯を作る原因になるのは主として糖分とミュータンス菌な一方で、歯周病は多種の口腔内の細菌が関係していると言われていることはご存じでしょうか。
まず、食べたものが口の中に残っていると、それらの口腔内の細菌がプラーク(歯垢)というネバネバした物質に変化します。
このプラークのように細菌が大量に繁殖してヌメヌメした物質は「バイオフィルム」と呼ばれています。
細菌の塊のバイオフィルムは、酸性物質なら歯の表面のエナメル質を溶かし虫歯になりますが、歯周病は歯ではなく歯茎に炎症を起こし、さらに歯茎そして歯を支えている骨の土台、歯槽骨を破壊しまうのです。
また、歯周病を引き起こす細菌は嫌気性といって空気を嫌う性質があります。
プラークが歯と歯茎の間のポケットと呼ばれる部分に入り込むと、そこは嫌気性細菌の絶好の住みかになります。
丁寧な歯磨きでプラークを毎日除去することが、歯周病の予防になによりも大切と言われているのはそのためです。

プラークは最近の格好の住みか
口腔内ケアをしないと虫歯と歯周病が同時に発生することも
プラークが取り除かれないと唾液の中に含まれる石灰分を吸収して歯石という硬い物質に変わります。
歯石にはプラークが付きやすく、嫌気性の細菌を守る培地のような存在になります。
歯磨きだけでプラークは完全には除去できません。
定期的な歯石除去が必要なのはこのためです。
歯石を作る元になる唾液中の石灰分は酸性の物質で、歯から失われた石灰分を補う再石灰化を行う働きもあります。
歯は石灰分を失う脱灰と再石灰化が繰り返し行われていて、そのバランスが崩れると虫歯になるのです。
歯石を作る時に、悪玉の唾液中の石灰分は虫歯から歯を守る役割も果たしています。
このような仕組みになっているので、歯石の付きやすい人は虫歯になりにくいとも言えます。
ただし、口腔内ケアをきちんとしないと虫歯と歯周病が同時に発生するリスクもあるのです。
虫歯菌と歯周病菌はどちらも困った存在ですが、人は細菌と共存して生きていかなければなりません。
除去することはできない以上、口腔内ケアで歯周病菌や虫歯菌が暴れ回らないようにすることが大切なのです。
銀座の歯医者は銀座並木通り歯科